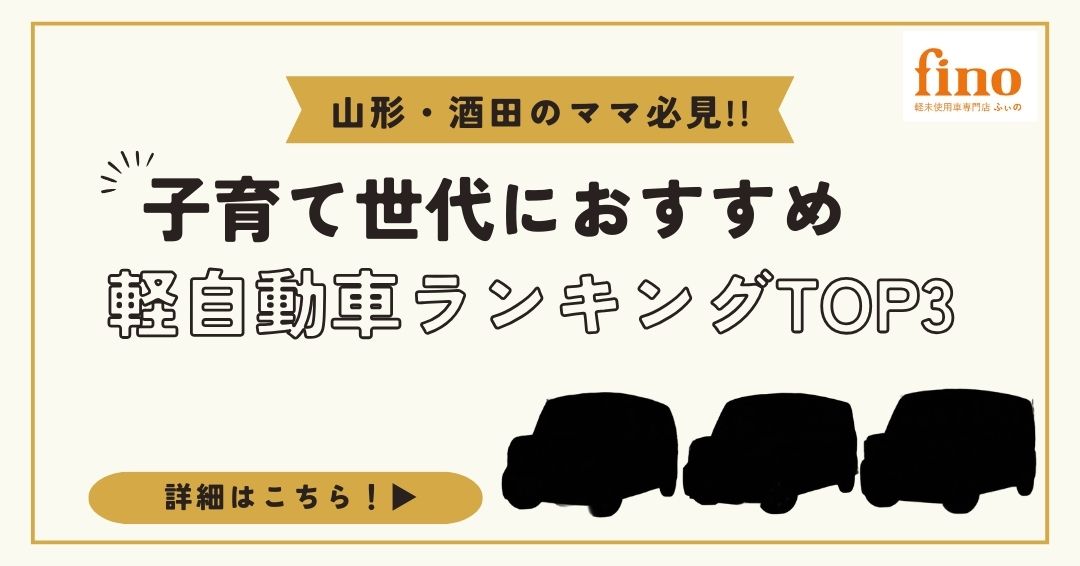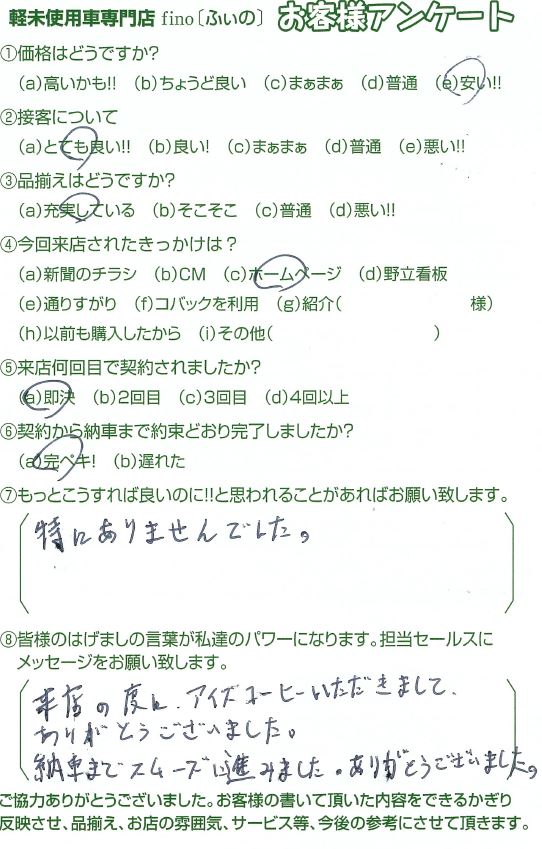-
 スタッフブログ
2025.12.30
スタッフブログ
2025.12.30
雪国では軽が不利って本当?山形で逆転現象が起きる理由
「雪が多い地域で軽自動車は不利」と聞いたことはありますか?車体が軽いので滑りやすい、パワーが弱いので深雪にハマってスタックしやすいといわれることがあります。 しかし、山形県では軽自動車が大人気で、軽自動車保有率は全国でもトップクラスです。大雪が避けられない地域なのに、なぜこれほど軽自動車が選ばれているのでしょうか。 今回はその理由を、道路環境や暮らし方、冬の交通事情といった山形特有の条件から詳しく解説します。「雪国なのに軽自動車が主役」の理由を知ることで、購入を検討中の方にも新しい視点が生まれるはずです。 なぜ一般的に「雪国で軽自動車が不利」といわれるの? 雪道を強い車の特徴として、主に以下の3つが挙げられます。 ・重量が重い・駆動方式が4WD・最低地上高が高い 一般的に、雪道では重い車の方が滑りにくいといわれています。重い車のほうがタイヤでしっかりと地面をつかむためグリップ力が高いためです。2025年時点、最軽量クラスの軽自動車と普通自動車はそれぞれスズキ アルトの680kgとマツダ マツダ2で1,040kg。その差は360kgも違います。 また、駆動方式にも大きく左右されます。エンジンの力を4つのタイヤすべてに伝える駆動方式である4WD(四駆)が雪道には有利です。前輪が車を引っ張る力、後輪が車を押す力の両方を活用できるためです。 最後に、最低地上高が高いことも挙げられます。最低地上高とは地面から車の腹下の高さのことで、これが低いと少し雪が積もっただけでタイヤが設置しにくくなり、亀のような状態になり前に進むことができなくなります。 しかし実際には、今の軽自動車は十分に進化しています。重量は普通車より軽くなるものの、4WDが選べ、最低地上高も高めなスズキ ハスラー・ジムニーのような軽自動車もありますし、横滑り防止装置など安全装備も進化しており、さらにスタッドレスタイヤの性能も向上しています。 山形で「軽が不利にならない」最大の理由 山形県では、除雪の速さがむしろ軽自動車に追い風となっています。地域にもよりますが、市街地の除雪がとても早く行われます。夜中から早朝にかけて除雪車が入り、通勤時間帯には道路がほぼ走行可能な状態になっていることも少なくありません。除雪されている道路を走れば、最低地上高が低めの車でも通勤、買い物、送迎などは問題ありません。深い雪の中を走るということを避けようと思えば避けられるのです。 また、山形県は車社会なので家族1人1台が車を持つ家庭もあります。維持費と雪道の走りやすさを天秤にかけ、維持費の安さを選択することも合理的なのです。中には普通車も持っており、深い雪や高速道路を走る人はそちらを使うなど使い分けするケースもありますが、決まった短距離のルートを走る使い方であれば「軽で十分だ」と判断する人が多いということですね。 また、山形では軽自動車でも4WDを選ぶ人が少なくありません。中古市場でも4WD比率が高く、「まず4WDありき」で車選びをする方が多いです。加えて、先に話したように最近のスタッドレスタイヤは性能が向上しており、雪道でのグリップ、排雪性、温度変化への耐性など、昔の「軽のタイヤは不利」という常識はなくなってきています。 まとめ 一般的に雪国では軽自動車が不利と言われる反面、山形県では軽自動車のシェアが大きいことが現実です。生活圏のコンパクトさ、除雪の速さ、4WDとタイヤ性能の向上などが組み合わさることで、山形県では普通車よりむしろ軽自動車と判断される方が多いのです。 「雪国だから普通車が有利」という考えは確かに間違いではないのですが、生活スタイルによっては「軽自動車で十分」ともいえます。自分に合った車を選ぶことが、もっとも安全で経済的、そして賢い判断といえるでしょう。 -
 スタッフブログ
2025.11.29
スタッフブログ
2025.11.29
軽自動車の除雪・発進トラブル対策!雪にハマったときどうする?
冬の山形では、朝起きたら車が雪に埋もれていたり駐車場から出ようとしてタイヤが空回りすることがあります。特に軽自動車は車体が軽いため、雪にハマる(スタックする)リスクが普通車より高めです。 この記事では、雪国でよくある「発進できない」トラブルを防ぐための除雪と脱出のコツを、軽自動車向けに解説します。 なぜ軽自動車は雪にハマりやすいの? 軽自動車の特徴である「軽さ」は以下の理由で雪道では不利になることがあります。 ・タイヤが雪面を押しつける力が弱く、グリップ力が落ちる・駆動輪の下に雪が詰まりやすく、空転しやすい・車高が低い車種では腹下が雪に乗り上げやすい つまり、軽自動車が動けなくなるのは単にパワー不足ではなく、接地力と車高の問題が大きく関係しています。 雪にハマったときは、まずは除雪! 焦ってアクセルを踏む前にしっかり除雪することが重要です。雪にハマった状態では、タイヤが雪を掘ってしまったりうまく接地しなかったりして、どんなにパワーをかけても抜け出せません。 1. タイヤ周りを掘る2. マフラーの周囲を掘る3. タイヤの下に滑り止めを敷く まず、前後のタイヤのまわり(特に駆動輪側)をスコップで掘ります。腹下に雪が詰まっている場合は、車の下部も除雪しましょう。車が雪に乗り上げた状態では、タイヤが空転しても進みません。 次にマフラー周りの除雪です。排気口が雪で塞がれると、排気ガスが車内に充満して一酸化炭素中毒になってしまう危険があります。暖気運転中に排気が詰まると非常に危険なので、必ず除雪してからエンジンをかけましょう。 最後に、タイヤの下に次のようなものを敷くと脱出しやすくなります。 ・砂や砂利・段ボール、ゴムマット、タオルなど・脱出マット 新聞紙など薄い紙はすぐ破れて滑るため、厚手の素材を選ぶと効果的です。 雪にハマったときの発進テクニック 発進方法にも工夫が必要です。力任せにアクセルを踏むとタイヤが雪を掘ってさらに沈み込むため逆効果です。 ・前進と後進で前後に車を揺らす・アクセルを軽く踏む・トラクションコントロール(TRC)をオフにする 「D(前進)」と「R(後退)」を交互に切り替えつつアクセルを軽く踏みます。少しずつ前後に動かして雪を押し固めるイメージです。また、アクセルは軽く踏みましょう。アイドリング付近の回転数で十分です。強く踏むとタイヤが空転し、雪面がツルツルになってしまいます。トラクションコントロール(横滑り防止)が装備されている車は、一時的にオフにすると動き出しやすい場合があります。トラクションコントロールが作動すると空転を抑えようとしてエンジン出力が制限され動けないことがあるためです。脱出後は安全のため必ずオンに戻してください。 雪でのスタック対策にできること 雪でスタックして困らないように、日頃準備をすることも大切です。 ・スタッドレスタイヤの点検・冬用装備を積んでおく 雪国ではタイヤの溝だけでなく、ゴムの柔らかさも重要です。3年以上経過したスタッドレスは硬化して性能が落ちます。2〜3年での交換を目安にしましょう。また、雪を掘ったり車を引っ張るために以下のアイテムを積んでおくとよいでしょう。 ・スコップ・脱出用のマット・手袋や長靴・牽引ロープ 荷室に収まるサイズのものが多く、軽自動車でも十分に積載可能です。 まとめ 雪にハマったときに大切なのは、焦らず冷静に対処することです。 ・タイヤ周りや腹下、マフラー出口を除雪する・軽いアクセルで前後に車を揺らす・どうしても発進できない場合、ロードサービスを呼ぶ 軽自動車でも正しい対処法を知っていれば雪道は十分に走り切れます。冬の山形を安全に過ごすために、日頃から備えを整えておきましょう。 -
 スタッフブログ
2025.10.31
スタッフブログ
2025.10.31
山形の坂道・峠道に強い軽自動車とは?馬力とトルクの違いから考える
山形県は蔵王や月山など山々に囲まれ、坂道や峠道を走る機会が多い地域です。買い物や通勤で街中を走るだけなら軽自動車の力でも十分ですが、勾配のきつい山道や長い峠道になると「軽で大丈夫?」と不安になる方もいるかもしれません」。 この記事では、軽自動車の性能を左右する「馬力」と「トルク」の違いを解説し、現行モデルの中から山形の坂道に強い一台を探っていきます。 馬力とトルクの違いを理解しよう 自動車の坂を上る能力「登坂力」に関係するのが、馬力(出力)とトルク(回転力)です。 馬力(ps):スピードを出す力。どれだけ速く走れるかを示す。トルク(N・m):車を動かす力。止まった状態から動き出すときや、坂を登るときに重要。 坂道ではトルクが重要です。馬力が高くてもトルクが弱いと上り坂でエンジンが唸るばかりでスピードが出ません。逆にトルクが強いと、アクセルを少し踏むだけで力強く登っていけます。軽自動車の場合、最大トルクはターボエンジンの有無で大きく変わります。NA(自然吸気)エンジンでは60N・m前後、ターボ付きなら100N・m近いモデルもあります。この差が坂道での余裕に直結します。 たとえるなら、馬力はその荷物をどれだけ速く遠くに運べるか、トルクは腕力で荷物を持ち上げる力とイメージすると分かりやすいです。 軽自動車は馬力が同じでも走りが違う 日本の軽自動車は規格で「最高出力64PSまで」と決められています。そのため、どのメーカーの軽ターボもカタログ上の馬力はほぼ横並びです。 ではなぜ走りに違いが出るかというと、以下の特性が影響するためです。 ・車両重量の違い(軽いほど有利)・最大トルクの太さと発生回転数・ギア比やCVT制御の特性 特に坂道や峠道では「低回転から太いトルクが出せるか」が鍵になります。 トルクが強く普段使いにもおすすめの軽自動車を紹介 ・ホンダ N-BOX ターボ 64PS / 6000rpm、104N·m / 2600rpm 背の高いボディで重さがあるが、低回転からトルクが太く、登坂力に余裕あり。 ・スズキ ハスラー ターボ 64PS / 6000rpm、95N·m / 3000rpm SUV風デザインに実用的なトルク。雪道や坂道でも安心。 ・ダイハツ ミライース 49PS / 6800rpm、57N·m / 5200rpm 力強さはないが、軽量ボディのおかげで市街地は軽快。峠ではやや苦しい。 ・スズキ アルト(NA) 48PS / 6500rpm、58N·m / 5000rpm 燃費優先だが、軽さでカバー。ちょっとした坂道なら十分対応可能。 山形で坂道に強い軽を選ぶなら? 山形のように峠道や雪道が多い地域では、以下の条件を満たす軽が安心です。 ターボエンジンで低回転からトルクが太いこと車重が軽いこと4WD設定があること(冬の安全性) 「馬力が大きい=坂道に強い」と思われがちですが、実際はトルクの出方と車重が坂道性能を大きく左右します。山形のような勾配のきつい地域で軽自動車を選ぶなら、馬力数値だけでなくトルク特性や駆動方式までチェックすることが大切です。 軽でも選び方次第で、峠道や雪道をストレスなく走れる相棒が見つかりますよ。 -
 スタッフブログ
2025.09.30
スタッフブログ
2025.09.30
車社会 山形県の軽自動車普及率を、全国平均と比較した
山形県といえば、広大な山間部と雪深い冬が特徴的な地域です。公共交通機関は都市部以外では本数が限られ、日常生活の足として車が欠かせません。そんな山形県で特に目立つのが軽自動車の存在です。山形県では実際どのくらい走っているのでしょうか?今回は、全国平均と比較しながら山形の軽事情を掘り下げてみます。 山形県は世帯あたり軽自動車普及台数で全国トップクラス 全国軽自動車協会連合会の調査によると、2024年時点で山形県の軽四輪車の「世帯あたり普及台数」は 100世帯あたり約99.7台。これは全国平均の 約54.5台 を大きく上回っています。つまり、山形では「ほぼ1世帯につき1台の軽自動車を持っている」計算になり、家庭によっては2台、3台と複数台を所有するケースも少なくありません。 この背景には以下の理由があると考えられます。 ・公共交通の不便さから世帯ごとに複数台が必要になる・軽自動車は車体価格や維持費が安く、保険料や税金も抑えられる・狭い生活道路でも扱いやすい 山形県民にとって、軽自動車は単なる移動手段の枠を超えて「生活必需品」といってもよいでしょう。 山形において、乗用車に占める軽の割合は中位レベル 一方で「乗用車全体に占める軽自動車の割合」で見ると、山形県は全国的に突出して多いわけではありません。2024年のデータでは、山形の割合は 約66.5%。これは全国平均の 約41% を確かに大きく上回りますが、沖縄(約78%)、鹿児島(約75%)、長崎(約74%)、秋田(約70%)といった県には及びません。 つまり「世帯当たりの普及度」ではトップクラスながら、「割合ベース」では全国的に中の上といった位置づけになります。ここに山形の特徴が見えてきます。 一見矛盾するこの数字の違いには、山形ならではの生活スタイルがあります。 ・複数台持ち世帯が多い・普通車との使い分け 地方では夫婦それぞれが1台ずつクルマを持つのが一般的です。さらに親世代や子世代と同居していれば、家に3台以上クルマが並ぶことも珍しくありません。 雪道や長距離移動、荷物の運搬などには普通車を使い、買い物や通勤には軽を使うという棲み分けがなされています。そのため軽が多い一方で、普通車の需要も根強いのです。 このように、台数ベースでは軽が目立つけれど、割合ベースでは普通車も一定数あるため「突出して軽一辺倒」という状況にはなっていません。 まとめ 山形県は車社会の典型例といえる地域であり、軽自動車の普及度は全国でもトップクラスです。 世帯あたり普及台数 → 全国平均のほぼ2倍で“ほぼ1世帯1台”乗用車に占める割合 → 全国平均より高いが、突出した上位県ほどではない この数字から見えてくるのは「軽が生活に深く浸透している一方で、普通車とのバランスを取りながらクルマを使い分けている」という山形県の姿です。雪国特有の生活環境と、地方ならではの交通事情が生み出した結果ともいえるでしょう。 -
 スタッフブログ
2025.08.30
スタッフブログ
2025.08.30
2024年末に開通した新庄古口道路。どんな経緯、狙いで作られたの?
国道47号は、宮城県仙台市と山形県酒田市を結ぶ全長およそ155kmの主要国道。なかでも新庄市から戸沢村を通って最上川沿いに西へ向かう区間は、最上地域と県内外を結ぶ大動脈のひとつとなっており、観光・物流・通勤通学のすべてで欠かせない道路です。 しかし、この区間は山間部を縫うように走っており、線形が悪くカーブや急勾配が多いことから、交通の流れが滞りやすく、特に冬季は積雪や路面凍結によって事故のリスクも高い状況が続いていました。 新庄古口道路の概要 こうした課題に対応するために建設されたのが、新庄古口道路を含む新庄酒田道路です。この道路は現在の国道47号をバイパスする形で新設されたもので、片側1車線の対面通行となります。途中にはトンネルや橋も含まれ、できる限り直線的なルートで整備されています。 新庄古口道路の新庄市大字升形から戸沢村大字津谷の約6.0kmが2024年12 月7 日(土)に開通し、これで10.6kmすべてが開通したことになりました。2002年度から計画がスタートし、土地の確保や調査、工事を経て、22年での完成です。 なぜこの区間の整備が急がれたのか? 新庄古口道路は国道47号の混雑緩和を目的に整備されました。混雑が緩和すると、安全性の向上、所要時間の短縮、緊急輸送路の強化などの効果が期待できます。 現道の国道47号はカーブや狭い部分が多く、対向車とのすれ違いや大型車の通行が困難な箇所が多く存在します。冬季には事故も多発しており、ドライバーにとっては常に緊張を強いられるルートでした。新庄古口道路では線形を改善し、トンネルなどを活用して急カーブや急勾配を回避。より安全な通行を実現しています。 また、山形県の日本海側と内陸を結ぶ国道47号は、災害時の緊急輸送路としても重要です。地震や大雨などで既存道路が寸断された場合でも、新庄古口道路が代替ルートとして機能することが期待されています。 地域経済や観光への波及効果も大きいと見られています。酒田港には外国のクルーズ船も寄航するプランが用意されています。新庄古口道路の整備により、酒田港と内陸部のアクセスも強化されます。 まとめ:地域の未来をつなぐインフラとして 2024年末に開通した新庄古口道路は、単なる道路整備にとどまらず、安全性・時間短縮・災害対応・地域振興といった複数の目的を果たす「地域のライフライン」として大きな意味を持つ存在です。 新庄市と最上地域をより強く結びつけ、山形県全体の交通網を進化させるこの新しいバイパス。今後どのように活用され、地域に根づいていくのか注目されます。交通の便がよくなることは、単に“便利になる”以上に、その土地の未来に直結しているといえるかもしれません。 -
 スタッフブログ
2025.07.31
スタッフブログ
2025.07.31
なぜ山形のガソリン価格は高い?理由と対策を紹介
「なんでこんなにガソリン高いの?」。山形県で車を使う人の多くが、そう感じたことがあるのではないでしょうか。全国的にガソリン価格が高騰している今、山形県では特にその傾向が強く、地域によってはリッターあたり180円を超えるかもしれません。 実は、ガソリン価格の高さには、全国共通の要因だけでなく、山形特有の事情が大きく関係しています。この記事では、なぜ山形のガソリン価格が高くなりやすいのか、他県との違いを交えながら詳しく解説し、実践できる対策も紹介していきます。 山形県のガソリン価格は、他県と比べて高い傾向にある 山形のガソリン価格が本当に高いのかデータを見てみましょう。 2025年7月末でのレギュラーガソリン全国平均はおよそ166円/L。一方で、山形県内では180円を超える地域も多く、ガソリンスタンドによっては185円/L近い価格が表示されていることもあります。 山形のどの地域でも、全国平均より明らかに高いの水準です。宮城県168円/Lや新潟県162円/L、秋田県170円/Lと比較しても、山形はガソリンが高くなっています。 なぜ山形県のガソリン価格は高いのか? 山形県のガソリン価格が全国平均を上回り続ける背景には、複数の要因が重なっています。 まず第一に挙げられるのは、地理的なハンデです。山形県にはガソリンの原料である原油を精製する製油所が存在しません。東北地方で最も近い製油所は宮城県仙台市にありますが、山形県内に流通させるには県境の山を越える必要があり、輸送コストがかさみます。 ただし、この「製油所からの距離」という観点で言えば、青森県や秋田県の方が不利に見えるかもしれません。しかし、両県には複数の港があり、燃料を船便で直接取り込むルートがあります。船による大量輸送が可能なため、コストを抑えられているの。一方、山形県にも酒田港がありますが、港から県中央部や南部への輸送はやはりトラックに頼らざるを得ず、距離や山間部の地形がコスト増の原因になっています。 また、山形の都市構造も価格高騰の一因です。山形県は都市が比較的小規模で、人口が広範囲に分散しています。ガソリンスタンドが点在する構造になりやすく、価格競争が起きにくいという問題があります。激しい値下げ合戦が生まれにくく、価格が高止まりする傾向があるのです。 さらに、営業形態の違いも影響します。山形県内ではフルサービス型のガソリンスタンドが多く残っており、セルフ式に比べて人件費や運営コストがかかります。これらの費用はガソリン価格に反映され、同じ地域内でもフルサービスとセルフの間で数円以上の差が出ることもあります。都市部や競争の激しいエリアではセルフ化が進んでいるため、相対的に山形は高く見えてしまうのです。 自動車にかかるお金を抑えるために 山形では車が欠かせませんが、ガソリン代や維持費の負担は大きいもの。そこで、燃費の良い軽自動車に乗ることをおすすめします。 「ホンダ N-BOX」や「スズキ アルト」は燃費性能が高く、リッターあたり実燃費で20km前後走るモデルもあります。普通車にも燃費がいいモデルはありますが、車検や自動車税などの費用が軽自動車より高くなりがちです。毎日の通勤や買い物、送迎など、日常使いに最適なのはやはり軽自動車といえるでしょう。 また、日常の運転習慣も見直してみましょう。アイドリングを減らす、タイヤの空気圧を適切に保つ、重量のある不要な荷物はおろすなど小さな積み重ねで大きな差が出ます。 このように、車が生活に不可欠だからこそ、どう付き合うかが重要です。ガソリン価格は確かに高いですが、できる範囲で賢く支出を抑えていくことが、長く快適に暮らすために大切だといえるでしょう。 -
 スタッフブログ
2025.07.05
スタッフブログ
2025.07.05
酒田市北側、遊佐象潟道路っていつできるの?工事計画を見てみよう
2019年に山形県が策定し2024年にもアップデートされた山形県道路中期計画2028。いろんな道路整備の方針が書かれていますが、ここでは酒田から近い「日本海沿岸東北自動車道」、特に遊佐町から秋田県にかほ市を結ぶ「遊佐象潟道路(ゆざきさかたどうろ)」について紹介します。 酒田市のすぐ北側、遊佐町を通るこの道路。実は酒田市に住んでいる人にとってもメリットがある道なんです。 遊佐象潟道路は山形県と秋田県をつなぐ重要な道路になる 赤枠が遊佐象潟道路(未開通) 遊佐象潟道路は遊佐町から秋田県側の象潟(きさかた)までをつなぐ、全長およそ18kmの日本海側東北自動車道です。日本海側を縦に走るこの道路は、将来的には新潟から青森までつながる予定で、国の重要な幹線道路でもあります。 「遊佐町の道路って、酒田の自分には関係ないのでは?」と思うかもしれません。でも実は、酒田市に住む人たちにとっても大きなメリットがあるんです。 まず一番のポイントは、秋田県南部とのアクセスがグッと良くなること。2025年6月時点で酒田市から秋田県南部に行こうとすると国道7号を使うしかなく、交通に時間がかかっていました。しかし、遊佐象潟道路が開通すれば、酒田ICから自動車道を降りることなく北上できるようになり、酒田から秋田への移動がぐっと楽になります。 たとえば秋田県側に親戚がいたり、出張で行ったり、温泉や観光で遊びに行くことがある人にとっては、まさに便利そのもの。反対に、秋田から酒田へ来る人たちにとってもアクセスが良くなるので、交流が活発になったり、観光客が増えたりすることも期待されます。 さらに、物流の面でも大きな意味があります。酒田港と秋田方面を結ぶルートが強化されることで、輸送がスムーズになり、地元企業にとってもメリット大。トラックの移動時間が短くなればコスト削減にもつながりますし、災害時の緊急輸送ルートとしての役割も担えるようになります。 遊佐象潟道路の工事は計画から遅れている この便利な道路は、実は県境部分の計画から工事が遅れています。以前は2026年度に山形と秋田の県境部10.6kmが開通する計画でした。しかし、2024年末の秋田河川国道事務所と酒田河川国道事務所の発表によると、吹浦ICから小砂川IC間の8.3kmは計画見直しが入りました。開通予定時期も定まっていません。なお、山形県遊佐町の遊佐鳥海ICから吹浦IC間の2.3kmは変わらず2026年に開通予定です。 工事が遅れている理由は大きく分けてふたつです。まず、沿線に国指定史跡「鳥海山」や「旧登拝道」があり、環境への配慮のため慎重な整備が必要になったこと。そして、2024年の豪雨の影響で計画していた工事方法が困難になったことです。 とはいえ、工事自体がなくなったわけではありません。全線がつながれば、酒田市を取り巻く道路ネットワークが一気に強化されることになるので、行政もこの道路の重要性はしっかり認識していていることでしょう。 道路のことは普段あまり意識しないかもしれませんが、実は日常生活のあらゆることに関わっています。遊佐象潟道路の整備が進めば、通勤・通学、買い物、観光、物流、医療、災害対応など、酒田市の暮らしに直結するさまざまな場面で「よかったな」と感じられる場面が増えるはずです。 今はまだ完成前ですが、地元のインフラとして大きな期待が寄せられているこの道路。これからの進捗を見守りつつ、少しずつその便利さを体感できる日が近づいてきています。酒田での暮らしが、またひとつ便利に、安心に変わっていく。そんな未来を楽しみにしたいです。 -
 スタッフブログ
2025.06.23
スタッフブログ
2025.06.23
第19回やまがた軽未使用車まつり in 山形ビックウイングに参加します!!
こんにちは、軽未使用車専門店ふぃののブログ担当です!! 2年ぶりに軽未使用車専門店ふぃのは やまがた軽未使用車まつり実行委員会主催の 第18回やまがた軽未使用車まつり in 山形ビックウイングに参加いたします。 2025年6月27(金)28(土)29(日)の 3日間は山形ビックウイングにて やまがた軽未使用車まつりにご来場ください。 オールメーカー500台大量展示でほしい車が きっと見つかります! WEB予約特典で、最大10,000円分の Quoカードプレゼントします。 詳しくは下記ボタンをクリックし、特設サイトをご確認ください。