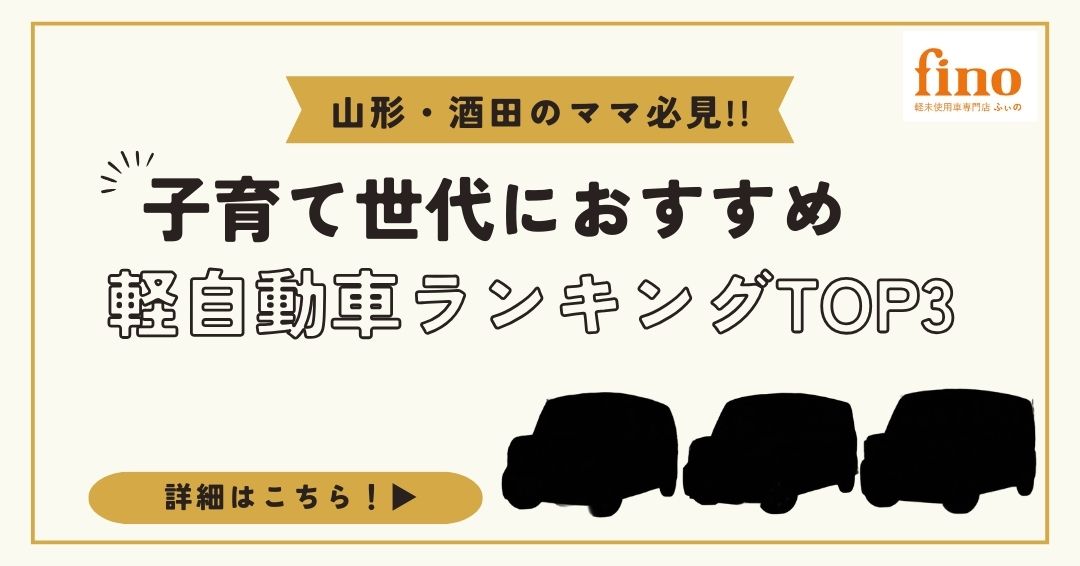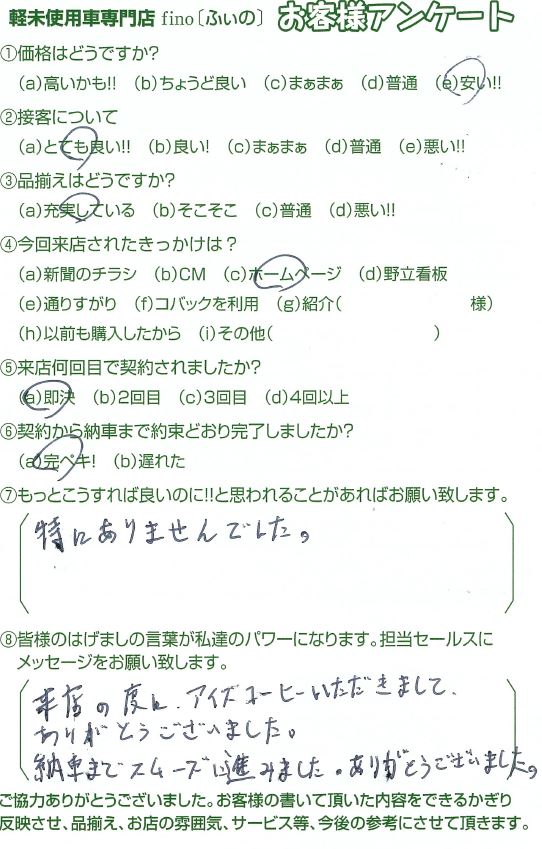-
 スタッフブログ
2023.01.25
スタッフブログ
2023.01.25
免許取り立てでも運転したい!おすすめの車をご紹介!
免許を取って、どんな車に乗ろうかとワクワクしながらも、初めて車に乗ることに不安や恐怖を感じるのは自然なことです。 車の購入が人生初の大きな買い物だという方は特に、後悔のないように車を選びたいのではないかと思います。 少しでも運転のプレッシャーを減らせるように、免許取り立ての方でも運転しやすい車の条件と車種をご紹介します。 また、新車、中古車、未使用車のうち、どれが初めての車におすすめなのかもご紹介します。 これから車を手に入れようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。 免許取り立ての人におすすめな車の条件 免許取り立ての方におすすめの車の条件をいくつかご紹介します。 コンパクトで小回りが利く 初心者のうちは、車体の大きさをイメージすることが難しく、バックや幅寄せに苦労します。 バックや幅寄せといった場面でできるだけプレッシャーを感じないように、軽自動車や小型普通車といったコンパクトで小回りが利く車がいいでしょう。 視界が広い 十分ゆとりをもって周囲の安全確認をできるように、視界が広い車がおすすめです。 フロントウインドウとリアウインドウが大きいことだけでなく、三角窓が大きくフロントピラーが細めであれば、斜め前方の死角が少なく運転がしやすいです。 先進安全機能が搭載されている 頼りすぎは禁物ですが、先進安全機能が搭載されていると安心感が大きく上がります。 バックモニターがあれば余裕をもってバック駐車ができ、車間距離制御装置があれば、不用意に車間距離を詰めすぎてヒヤリとする場面を減らせます。 免許取り立ての人におすすめな車3選 ホンダ N-BOX ホンダ N-BOXは、大きな三角窓と極細ながらも剛性の高いフロントピラーを採用しており、良好な視界をもった車です。 軽自動車の中では特に車高が高く、前方の見通しがよく運転しやすいです。 車両や人を検知してブレーキを自動的にかけてくれる衝突被害軽減ブレーキ機能や、バックの際に後方の障害物の接近を知らせてくれるパーキングセンサーシステムなどの先進安全機能「Honda SENSING」により安全性能が高められています。 スズキ スペーシア スズキ スペーシアは車高が高めであるにもかかわらず小回りが利く運転しやすい車です。 運転席からボンネットを視認できるだけでなく、リアウインドウとリアクォーターウィンドウが大きく後方視界支援ミラーがついているため、死角が非常に少ないです。 左右2つのカメラで前方の車や歩行者を検知するデュアルカメラブレーキサポートや車線中央を維持するようにステアリングの支援をしてくれる機能などの先進安全機能「スズキ セーフティ サポート」が装備されており、ヒヤリとする場面を減らしてくれます。 ダイハツ タント ダイハツ タントは、極細ピラーにより視界が広く、小回りが利き狭い道でもストレスなく運転できる車です。 ボンネットの長さが短く運転席からでも先端を視認できるため、安心感があります。 車線逸脱警報や標識認識などの安全先進機能「スマートアシスト」が装備されているので、安全面でも安心して運転できます。 はじめての車は新車、中古車、未使用車のどれがおすすめ? 免許を取り立ての方が初めて購入する車は、新車、中古車、未使用車のどれがいいのでしょうか。 新車は一からオプションやグレードを選べて自分好みの車にすることができますが、高価です。こすったりぶつけたりするリスクを考えると、せっかく買ったのに積極的に乗ろうという気持ちが萎えてしまうかもしれません。 中古車は憧れの車を安価に購入できるかもしれませんが、コンディションが良いとは限りません。不慮のトラブルがあった際に車の知識が少ない初心者のうちは非常に苦労するでしょう。 そこでおすすめしたいのは、未使用車です。 自分好みのカラーやオプションを選ぶのは難しいですが、使用歴のない新車同然の車をお手頃な価格で手に入れることができます。 万が一こすったりぶつけたりして車を傷つけてしまっても安価な分、精神的なショックは小さく済むでしょう。 また、納車までの期間が短く、すぐに乗れるのもポイントです。 まとめ 免許取り立ての方におすすめの車の条件と車種、新車・中古車・未使用車のどれがおすすめかをご紹介しました。 初心者でも適切な車を選べば快適にドライブを楽しめます。 ぜひお気に入りの一台を手に入れて、運転ライフを満喫してください。 気になる車種があれば、ぜひ当店で実際に見てみてください! -
 スタッフブログ
2023.01.11
スタッフブログ
2023.01.11
運転しやすい軽自動車とは?おすすめ車種をご紹介!未使用車という選択もあり!
もともと小回りが利いて運転しやすいといわれている軽自動車ですが、具体的にはどのようなところが運転しやすいのでしょうか。 自分に合った車を選ばないと、運転にストレスを感じ、せっかく購入した車を運転するのが億劫になってしまうかもしれません。 この記事では運転しやすい軽自動車の条件と、軽自動車の中でもより運転しやすいモデルをご紹介します。 また、新車・中古車に加わる選択肢として「未使用車」についてもご紹介しますので、今後購入する車を選ぶ際の参考にしてみてください。 運転しやすい軽自動車の条件 運転しやすい軽自動車の条件をいくつかご紹介します。 背が高く視界が広い 背が高くなるほどアイポイント(ドライバーの目線)の高さも上がり、前方の交通状況が把握しやすくなるというメリットがあります。 視界が広ければ目を凝らす頻度も減り、疲労度も下がります。 前後が短い 車の前後の長さが短いものほど、車両のサイズ感覚がつかみやすく、小回りが利いて運転しやすいという特徴があります。 特にボンネットが短いものは、車の前の長さをしっかり視認できるので、安心して運転できます。 運転サポートがついている 最近の軽自動車は、運転サポート機能が充実しています。 バックモニターやアラウンドビューモニターがあれば、運転席から目視できない箇所をしっかり視認できるので格段に駐車しやすくなり、対向車を検知してハイビームとロービームを切り替えるオートライトがあれば、せわしなく手動でライトを切り替えることなく前方の安全を確保できます。 他にも、ペダル踏み間違い防止機能、衝突被害軽減ブレーキ、車線維持システムなど、安全に走行するための機能がたくさんあります。 運転サポート機能に頼り切ってしまうのは厳禁ですが、運転サポート機能があれば安心感は大きく上がります。 おすすめの運転しやすい軽自動車3選 運転しやすいおすすめの軽自動車を3つご紹介します。 ホンダ N-BOX ホンダ N-BOXの全高は1.8m近くあり、軽自動車の中では車高が高めであるため、視界が広く運転しやすいという特徴を持っています。 フロントガラスと三角窓の面積も大きいので、前方の状況をストレスなく把握できます。 後方の障害物を検知してくれるパーキングセンサーシステムが搭載されており、駐車時も安心です。 ダイハツ タント ダイハツのタントはボンネットの長さが短いため、運転席からボンネットの先端を視認でき安心して運転できます。 リアウインドウも大きいため後方の確認もばっちりできます。 車高が高い分、視界が広くなるだけでなく、極端にかがむことなく楽に乗り降りできることもポイントです。 進入禁止や一時停止の標識を認識して知らせてくれる標識認識機能や、車道の中央を走行するように維持してくれるレーンキープコントロールといった安全先進機能「スマートアシスト」が装備されているので、不安や緊張を軽減してくれます。 スズキ ハスラー スズキのハスラーは、車高が高めでアイポイントも高くなるので、運転しやすい車です。 車間距離を保ちながら自動的に加減速してくれるクルーズコントロールや、前進時だけでなく後退時にも危険を察知してくれる衝突被害軽減ブレーキなどの安全装備も充実しています。 グレードによっては前後左右の状況を確認できるモニターカメラが装備されており、駐車時や発進時に心強い助けになってくれます。 新車や中古車でなく未使用車という選択もあり 新車は高いが、中古車はなんだか不安、という方は未使用車も検討してみてはいかがでしょう。 新車と中古車、未使用車の違い 未使用車は正式には「登録(届出)済未使用車」と呼ばれ、初度登録(届出)された車でありながら、実際には使用されていない車のことをいいます。 扱いとしては中古車ですが、実際には試乗や展示での使用すらされておらず、ほぼ新車同然といえます。 なぜこのような車が生まれるのでしょうか。 それには、ディーラーのノルマが関係しています。 実は新車の販売台数は、車の生産数や注文数ではなく、車の「登録数」でカウントしています。 なので、ディーラーがノルマを達成するために、車を無理やりお客様に売って販売数を稼ぐのではなく、ひとまずディーラー側で車両登録しておくという方法を取ることがあります。 これが「未使用車」が生まれる仕組みです。 未使用車は、新車のようにお気に入りのグレードやカラー、オプション等を指定することはできませんが、その分納車が早く、安価に手に入れられます。 運転しやすい軽自動車をお探しなら、ぜひご来店ください! 運転しやすい軽自動車の特徴とおすすめ車種、さらに新古車についてご説明しました。 運転しやすい車ならば、安心で快適な運転ライフを過ごせます。 気になる車があれば、ぜひ一度ご来店ください! -
 スタッフブログ
2023.01.04
スタッフブログ
2023.01.04
最近の軽自動車はなぜ高い?理由を解説!お手頃なおすすめ車種も!
軽自動車といえば、街乗りに最適な気軽に購入できる車というイメージでしたが、ひと昔前に比べると高価格になりました。 軽自動車はなぜどんどん値上がりしているのか、どんな車が高価格なのかを解説します。 また、現在でもお手頃な価格で購入できる軽自動車と、反対に高価格で高性能な軽自動車をご紹介します。 購入をご検討の車とぜひ照らし合わせてみてください。 軽自動車はなぜ高くなったのか? 軽自動車が高価格になった理由をいくつか解説します。 安全に対する規制が厳しくなった 社会的な安全意識の高まりから、カメラやレーダーにより前方の車や歩行者を検知してブレーキが作動する衝突被害軽減ブレーキや、周囲の明るさを検知して自動でライトをオンオフするオートライト機能などを新車に搭載することが義務化されました。 メーカーの企業努力による安全機能の高性能化は喜ばしいことでもありますが、自動車の価格は必然的に上がってしまいます。 値段重視から機能重視になっていった 世の中のニーズに応えて、自由自在にアレンジできるシートやパワースライドドア、運転支援システムなど、機能や装備が充実した車種が増えてきました。 デジタル機器の発展によってできることも増え、非常に便利になった分、価格が上乗せされます。 原材料費が増加した 原材料費が高騰することで、自動車製造のコストもかさんでいます。 特に大きな影響を与えているのが、原油価格の高騰です。 プラスチック部品や化学製品などの原油を原材料としたものだけでなく、車に必要不可欠な金属部品も、加工に必要な燃料費が高騰することによって値上がりしています。 また、現在の車の多くに搭載されているデジタル制御機器も、半導体の高騰により高額になっています。 軽自動車の値段の歴史 20年以上前ならば100万円あれば新車で軽自動車が購入できましたが、現在は様々なオプション費用を考慮すれば200万円を超えることも珍しくありません。 昔の軽自動車に少し触れたのち、現在でも100万円以下で購入できる軽自動車をご紹介します。 反対に、本体価格が200万円オーバーの軽自動車もご紹介します。 なんと過去には新車で47万円の車も! 1979年5月に発売となった初代アルトは、なんと新車で47万円という低価格で大ヒットしました。 当時の軽自動車の価格帯は60万円程度だったのですが、ベニヤ板で作った後部座席、電動モーターのない手押しポンプ式ウィンドウウォッシャーなど、極端なまでのコストカットにより低価格を実現しました。 今でも、実は新車で100万円以下の車もある スズキ アルト スズキのアルトは、本体価格が新車で約95万円(タイプA・2WD)という100万円を切るお手頃な価格で購入できるモデルです。 低価格とはいえ、車線逸脱警報機能やふらつき警報機能などの「スズキ セーフティ サポート」が標準装備されているため、安全面でも安心です。 また、減速時のエネルギーを利用して発電・充電してくれる「エネチャージ」により、25.2km/Lという低燃費を実現した車なので、購入後の維持費もお手頃です。 ダイハツ ミライース ダイハツのミライースは、本体価格が新車で約92万円(タイプB “SA Ⅲ”・2WD)という低価格のモデルです。 衝突回避支援ブレーキや誤発進抑制などの「スマートアシストⅢ」という安全先進機能が装備されています。 軽量化と空気抵抗の低減により、25.0km/Lの低燃費を実現しました。 200万円オーバーの軽自動車 ホンダ N-BOX ホンダのN-BOXは、最上位モデルは225万円(N-BOX Custom L・ターボ コーディネートスタイル・4WD)という200万円超えの車です。 ゆったりと広い車内はとても快適で、こだわりの詰まった細かな収納は使いやすく便利です。 ブラウンカラーを基調とした内装はエレガントな印象です。 日産 ルークスハイウェイスター 日産のルークスハイウェイスターの最上位モデルの本体価格は、約200万円(Gターボ アーバンクロム プロパイロットエディション)です。 自動で車間距離を調節したりカーブのハンドル操作を補助してくれる「プロパイロット」機能を装備しており、高速道路での長時間のドライブを快適にしてくれます。 衝突回避アシスト機能や移動物検知機能などの安全装備もフル装備されています。 軽自動車は高くならざるを得ない 軽自動車が高くなった理由と、お手頃・高価格それぞれのおすすめ軽自動車をご紹介しました。 多機能化や原材料費の高騰によって軽自動車は高くならざるを得ません。 しかし、安全性や快適性が上がっているのは間違いなく、ユーザーにとって好ましいことです。 気になる車があれば、ぜひお店に足をお運びください。 -
 スタッフブログ
2022.12.22
スタッフブログ
2022.12.22
スライドドア搭載のおすすめ軽自動車を紹介!スライドドアのメリット・デメリットとは?
最近の軽自動車にはスライドドアを搭載したモデルが多くなってきました。 スライドドアはいくつもメリットがあります。例えば、広い開口部と低いステップは小さなお子様がいたり、ご高齢の方を乗せたりする場合には特に便利です。 ただ、便利とはいえスライドドアのデメリットも気になります。 この記事では、スライドドアを搭載したおすすめの軽自動車と、スライドドアのメリット・デメリットをご紹介します。 便利なスライドドア搭載車への乗り換えを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。 お値打ちなスライドドア搭載の軽自動車3種 スライドドアを搭載したお値打ちな軽自動車を3つご紹介します。 ダイハツ タント ダイハツタントは、前後のドアに柱(ピラー)を内蔵した「ミラクルオープンドア」により、大きく開口できるスライドドアを両側に搭載した車です。 価格は130万円台からあり、比較的お手頃です。 前席と後席の間の柱がないため、車の側面をほぼすべてオープンでき、乗り降りや荷物の積み下ろしなどが非常に快適です。 また、電子カードキーを携帯しておけば、車に近づくだけでスライドドアが開くので、たくさんの荷物で両手がふさがっていても鍵を探す手間が省けます。 スズキ ワゴンRスマイル スズキ ワゴンRスマイルは、140万円台からのハイブリッド車にパワースライドドアが装備されており、リモコン一つで開閉できます。 パワースライドドアの開閉途中で一時停止できる機能があるので、ドアを小さめに開けて、雨が入り込むのを防いだり、ちょっとした荷物を積み下ろししたりするのに便利です。 座席周囲は広々としていて、ゆったりとくつろげます。 スズキ スペーシア スズキスペーシアは両側パワースライドドアを搭載した車です。 150万円台から購入できるHYBRID Xモデルは、ドアロックを予約できる機能を有しており、パワースライドドアが閉まるのを待つ時間が省けます。 床も低めに設計されているので、小さなお子様やご高齢の方でも乗り降りが楽ちんです。 低めの床に加えて、天井が高めで前後にもゆとりがあるので、車内でもリラックスして快適に過ごせます。 スライドドア車のメリット・デメリット スライドドア車のメリットとデメリットを詳しく説明します。 スライドドア車のメリット 開口部が広い スライドドアの車は、通常のヒンジ式のドアを搭載した車に比べて、開口部が大きいのが特徴です。その分、乗り降りや荷物の積み下ろしが楽にできます。 乗り降りが楽ちん 開口部が大きく、隣の車や壁を気にせずドアをフルオープンにできるため、ご高齢の方や妊婦の方もストレスなく乗り降りできます。 ドアの開け閉めの際に、隣の車や壁にぶつける心配がない ヒンジ式のドアのように、勢いよくドアを開けたはずみで隣の車や壁にぶつかるようなことがないので、小さなお子さんがいても安心です。 風にあおられにくい ヒンジ式のドアは、突風にあおられて大きく開いてしまい隣の車や壁にぶつかってしまう恐れがあります。 スライドドアは風を受ける面積が小さいため、風にあおられる心配がありません。 スライドドア車のデメリット ドアの開け閉めに時間がかかる ヒンジ式のドアよりも開け閉めに時間がかかってしまうため、急いでいるときや雨が降っているときはイライラするかもしれません。 ドアを半開可能なモデルや、ドアロック予約機能を搭載したモデルなら、開け閉めにかかる時間を節約できます。 スライド部にがたつきが起こる恐れがある 経年劣化によって、ドアのスライド部分にがたつきが発生して、スムーズにドアの開け閉めがしにくくなるかもしれません。 ヒンジ式のドアに比べて複雑な構造であるため、修理費用も高額になりがちです。 長く使うためにも、不調を感じたら大きな故障になる前にディーラーや整備工場などに相談しましょう。 非電動タイプの場合、ドアの開け閉めに力が必要 スライドドアはヒンジ式のドアに比べて重いので、非電動タイプの場合、開け閉めが大変です。 リモコンやワンタッチで自動開閉できる電動パワースライドタイプなら、ヒンジ式のドアよりも開閉が楽ちんです。 スライドドア車は子育て世代におすすめ! スライドドアを搭載した軽自動車と、スライドドアのメリット・デメリットをそれぞれ紹介しました。 スライドドア車にはデメリットがいくつかありますが、それらを上回るメリットがたくさんあります。 特に子育て世代の方々には便利で快適だと感じられるでしょう。 スライドドアを搭載した軽自動車をお探しの方は、ぜひ一度お店に足をお運びください! -
 スタッフブログ
2022.11.30
スタッフブログ
2022.11.30
意外と知らないレギュラー、ハイオク、軽油の違いを解説
皆様はレギュラー、ハイオク、軽油の違いをご存じでしょうか。 どれも自動車に必要な燃料で、ガソリンスタンドにはこの3種類の燃料が売られていることがほとんどです。 しかし、車ごとにどの燃料を使うかが決まっており、間違えて給油してしまうと、場合によってはエンジンの故障につながります。 この記事では、レギュラー、ハイオク、軽油の違いと、これらを間違えて給油した場合に起こることを説明します。 レギュラー、ハイオク、軽油の違いを解説 まずはレギュラー、ハイオク、軽油の違いを解説します。 レギュラーガソリン レギュラーガソリンは、日本国内でもっとも広く使われている車の燃料です。 異常燃焼を起こさないように入れる添加物の割合である「オクタン価」がハイオクガソリンと異なります。 異常燃焼とはエンジン内の所定の場所・タイミング以外で発生する予期せぬ燃焼のことで、エンジンの故障を引き起こす恐れがあります。 JIS規格ではオクタン価が89以上のガソリンをレギュラー、さらに高い96以上のガソリンをハイオクとしています。 ハイオクガソリン 「オクタン価」がレギュラーガソリンよりも高い(ハイ)ものが、ハイオクガソリンです。 オクタン価を高めるためにコストがかかるため、レギュラーガソリンよりも1Lあたり10円ほど高価になります。 軽油 レギュラーとハイオクはガソリンの一種ですが、軽油は成分が全く違います。 ガソリンと軽油は原油から留出される温度が異なります。一般的にはガソリンは35〜180度、軽油は240〜350度で留出されます。 軽油はガソリンを抽出する過程で取り出せるので、ガソリンよりも低価格です。 軽油とガソリンは燃え方が違うので、軽油仕様車でないと軽油を使うことはできません。 また、「軽自動車」だからといって「軽油仕様車」であるというわけではありません。 なぜ車種によって使う燃料が違うの? なぜ車種によって使う燃料が違うのでしょうか。それは、車に求められる性能によって、適切な燃料が異なるからです。 国産の自家用車のほとんどはレギュラーガソリン仕様車です。 一般的な自家用車よりも高性能のエンジンを搭載したスポーツカーや海外製の自動車などは異常燃焼を起こす可能性が高いため、異常燃焼を抑制してくれるハイオクガソリンが必要です。 また、同じ量の軽油とガソリンを燃やすと軽油の方がより多くのエネルギーを生み出します。つまり、軽油はガソリンと比べて高出力で熱効率が高くパワフルということです。 軽油は速さよりも力強さが必要とされるショベルカーやトラック、バスなどで使われる傾向があります。 間違った種類の燃料を入れたときはどうなる? セルフサービスのガソリンスタンドも多いため、燃料の入れ間違いも少なくありません。 燃料を間違えて入れてしまった場合どうなってしまうのか、それぞれのケースごとに説明します。 レギュラー仕様にハイオクを入れる レギュラー仕様の車にハイオクガソリンを入れた場合、実は特に問題は起きません。 とはいえ、レギュラーとハイオクの違いは異常燃焼を起こさないようにするための添加剤の割合だけなので、特に性能がアップすることもありません。 ただし、メーカーによっては洗浄剤を入れているハイオクガソリンがあり、エンジン吸気系に汚れがつきにくくなるという副次的な効果があるようです。 ハイオク仕様にレギュラーを入れる ハイオク仕様車にレギュラーガソリンを入れても、すぐに不具合が起きるわけではありません。 多くのハイオク仕様車には、異常燃焼を検知してエンジンを保護する制御プログラムがあるためです。 しかし、レギュラーガソリンは前述したオクタン価が低いため、排気量の大きなハイパワーのエンジンを搭載したハイオク仕様車では、異常燃焼を起こし異音や振動が発生するリスクが高まります。 長い目で見ると、出力の低下や燃費の悪化、エンジンの劣化などの不具合が起こる恐れがあります。 レギュラー、ハイオク仕様に軽油を入れる レギュラー、ハイオク仕様車に軽油を入れてしまった場合、ガソリンの残量にもよりますが、しばらく走行することはできます。 しかし、そのままにしておくとマフラーから煙が出て、エンジンが不具合を起こし停止してしまいます。 間違えて給油してしまった場合は、すぐに修理工場や車を購入した店舗に連絡し、対応してもらいましょう。 軽油仕様にレギュラー、ハイオクを入れる 軽油仕様車にレギュラーまたはハイオクガソリンを入れてしまった場合、エンジンを始動することはできますが、異常燃焼により燃料ポンプや燃料噴射装置などが破損する恐れがあります。 この場合も、すぐに修理工場や車を購入した店舗に連絡し、対応してもらいましょう。 まとめ レギュラー、ハイオク、軽油の違いと、これらを間違えて給油した場合に起こることを説明しました。 レギュラーガソリンとハイオクガソリンを間違えた時には大きな不具合は発生しませんが、レギュラー・ハイオクガソリンと軽油を間違えると重大な問題が発生する恐れがあります。 こういった問題を未然に防ぐために、しっかり知識を身に付けることが大切です。 この機会に、お持ちの車や購入をご検討中の車について調べてみてはいかがでしょうか。 -
 スタッフブログ
2022.11.23
スタッフブログ
2022.11.23
燃費を上げる簡単な方法とエコな軽自動車3つを紹介!
物価が高騰している中、自動車の維持費を抑えたいと考えている方も多いのではないでしょうか。 中でもガソリン代の節約は、すぐに実践できるうえある程度効果も大きいのでオススメです。 近頃は家計への負担を少しでも小さくするために燃費のいい車が人気を博しています。 さらに、燃費を向上させる走り方を意識すれば、もっとガソリン代の負担を減らせるでしょう。 今回は燃費を向上させる方法をご紹介します。また、特に燃費のいい軽自動車をご紹介しますので、乗り換えを検討している方は参考にしてみてください。 車の燃費を向上させる簡単な3つの方法 車の燃費を向上させる方法として、以下の3つをご紹介します。 ・エンジンブレーキを使う・無駄な荷物は下ろす・定期的にメンテナンスする エンジンブレーキを使う ブレーキはガソリンを燃やして作った推進力を熱に変えてしまいます。 とはいえ、運転するときはブレーキを使わざるを得ないので、減速時には出来るだけエンジンブレーキを使うことをおすすめします。 アクセルを踏んで加速、アクセルを離して減速、もっと減速したいときはブレーキを踏む、というイメージです。 また、加速については周囲の車のことも考えて早めに交通の流れに乗ることをおすすめします。余裕をもって加速すれば、同乗者にも優しい運転になります。 無駄な荷物は下ろす 車重が重いと走行時の負荷が大きくなり燃費が悪化します。 具体的には、100kgの荷物を載せて走ると3%程度燃費が悪くなるといわれています。効果は小さいですが塵も積もれば山となります。それほど難しいことでもないのでおすすめの燃費向上策のひとつです。 余計な荷物を積みっぱなしにしないように気を付けましょう。 定期的にメンテナンスする 車の状態が悪ければ、様々な燃費向上策を講じても、十分な効果を発揮しません。 定期的にメンテナンスすることで、車をいい状態に保ちましょう。 特に以下の3点は、適切な状態にしておかないと車に負荷がかかり燃費が悪くなる原因になるので、こまめにチェックしましょう。 ・タイヤの空気圧・エンジンオイル・エアクリーナー 軽自動車のカタログ燃費と実燃費 車の燃費と一口に言っても、実は「カタログ燃費」と「実燃費」という2種類の意味があります。 両者の違いをしっかり知ることが、燃費のいい車を選ぶ手助けになります。 カタログ燃費と実燃費とは? カタログ燃費とは、「ある一定の条件の下で、決められたパターンに沿って走行したときに算出される燃費」のことです。平坦な道をエアコンやライトなどを使わずに走行した結果だと考えてください。 実燃費とは、その名の通り「ユーザーが実際に運転した際の燃費」のことです。 信号待ちや周りの車に合わせて発進と停止、加減速を繰り返したり、環境に合わせてエアコンやライトを使用したりするため、カタログ燃費と同じ燃費を実現するのはほぼ不可能です。 カタログ燃費と実燃費はなぜ違う? 実燃費は、カタログ燃費より2〜3割低下することが多いといわれています。 なぜこれほどの差が生まれてしまうのでしょうか。 実燃費とカタログ燃費の差を生み出す要因は、主に以下の3つです。 ・エアコンやライトなどの電装品の使用状況・寒暖や道路状況などの走行環境・ユーザーの運転の仕方 特にユーザーの運転の仕方によって大きな差がつくといわれています。 燃費を向上させる方法の中でご紹介したように、「ブレーキでなく出来るだけエンジンブレーキを使う」ことを心がけましょう。 このように実燃費とカタログ燃費には差がありますが、カタログ燃費がいい車種は、実燃費も優れています。 軽自動車の燃費ランキング 比較的燃費がいいといわれている軽自動車の中でも、特に燃費のいい車種をご紹介します。 なお、実燃費は人によって変わるため、カタログ燃費で比較します。 1位:スズキ アルト スズキのアルトは、カタログ燃費27.7km/Ⅼという非常に優れた燃費性能を誇るモデルです。 発電効率に優れたモーターでエンジンをアシストしてくれる「マイルドハイブリッド」を搭載したことで、軽自動車の中でNo.1の低燃費を実現しました。 衝突被害軽減ブレーキ機能や誤発進抑制機能など、事故を未然に防ぐ予防安全性能「スズキセーフティサポート」が装備されているため、安全性も兼ね備えています。 丸みを帯びたかわいらしい外観も愛着が持てます。 2位:スズキ ラパン スズキのラパンはカタログ燃費26.2km/Lという低燃費を実現したモデルです。 「Lapin(ラパン)」はフランス語でうさぎという意味。その名の通り、丸くてかわいらしいデザインです。 後部座席のみ倒したりフルフラットにしたり、シートアレンジも自由自在なので、収納に困ることもありません。 3位:スズキ ワゴンR スズキのワゴンRは、カタログ燃費25.2km/Lという燃費のいいモデルです。 背が高く、ゆとりのある広い室内空間を有しており、前方だけでなく後方のシートも前後スライドとリクライニングができるため、車内で快適に過ごせます。 豊富なカラーバリエーションも魅力的です。 まとめ 車の燃費を向上させる方法と、燃費のいい軽自動車をご紹介しました。 燃費のいい車を適切な方法で扱えば、家計にやさしい運転ライフを過ごせます。 気になる車がある際は、ぜひ一度お店に足をお運びください! -
 スタッフブログ
2022.11.17
スタッフブログ
2022.11.17
アウトドア派にオススメ軽自動車!4車を特徴とともに紹介
このコロナ禍でアウトドアに注目が集まり、キャンプや釣りなどの様々なアクティビティがぐっと身近になりました。 車で海や山に行ってアウトドアを楽しみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。 アウトドアに不適な車で山に行くと道が悪くて立ち往生することもあります。 最近ではアウトドア向けの軽自動車も増えています。 そこで今回はキャンプやフィッシング、スキー・スノボなどに活躍してくれる車を紹介します。 この記事を読んでスタックの心配をせず思い切りアウトドアを楽しめる車を選んでください。 アウトドア向きの軽自動車の条件とは? アウトドア向きの軽自動車は以下の条件が必要です。 ・荷物をたくさん積める大きな荷室・車内空間・悪路にも強い走行性能・オプションの装着しやすさ 荷室・車内空間の広さ ギアをたくさん積むことができるように、荷室・車内空間の広さが重要です。 車中泊をするのであれば、横たわれるスペースも必要でしょう。 フルフラット機能や小物を収納できるポケットなどの利便性の高さも大事なポイントです。 悪路にも強い走行性能 山道やぬかるみでも走破できる走行性能があれば、行ける場所が多くなります。 4WDでSUVタイプの軽自動車なら悪路も問題なく走れます。 4WDは4つ全ての車輪が駆動するタイプで、悪路を走ってひとつの車輪が浮いても他の車輪で地面を蹴って走行できます。 SUVは地上高が高い車が多く、大きな石や段差を難なく乗り越えられます。 オプションの装着しやすさ 近年のアウトドアブームに合わせて、アウトドア向けのオプションが増えてきました。 長い釣竿を車内の天井につけられるルーフラックがあれば、荷物の整理がしやすいです。 また、防水性能が高いゴム製のフロアマットを敷けば、汚れがちなアウトドア用品を車内に持ち込んでも車内を清潔に保てます。 車内泊をする人ならカーテンをつければ他人の目線や日光を遮って快適に過ごせます。 アウトドア派にオススメな軽自動車4選 アウトドアにもってこいの軽自動車を4つ紹介します。 ・スズキ ジムニー・スズキ スペーシアギア・スズキ ハスラー・ダイハツ ハイゼット スズキ ジムニー ひとりでもどんどんハードな場所に行きたいという方に特にオススメです。 4WDのSUVタイプでアウトドアにもってこいの軽自動車で、オフロード走行を前提にしたデザインなので、ぬかるみや雪道も安心です。 ジムニーの大きな特徴として、ラダーフレームが挙げられます。ラダーフレームのラダーとははしごのことです。 ジムニーはラダーに居室である箱が乗っているだけの構造をしています。たとえ無理な悪路を走り車体がねじれてもラダーだけが力を受ける構造です。 ジムニー以外の軽自動車のほとんどはモノコックと呼ばれる、フレームと居室が一体化している構造です。 フレームがねじれると居室もねじれてしまいます。 そのため、ジムニーはデコボコ道でも走破できるタフさがあります。 積載量を増やせるルーフラックや、車中泊にも対応できるカーテンなど、アウトドア向けのオプションも充実しています。 無骨ながらも可愛らしさがある外観も素敵です。 スズキ スペーシアギア スペーシアギアはアウトドアに特化していますが、普段使いの利便性も欲しいという方にオススメです。 スペーシアギアは4つのシートを別々に折りたたんだりスライドできるため、どんな形状の荷物も乗せやすいです。 フルフラットにもできるので、車中泊にもぴったりです。 スペーシアのアウトドア特化版であるだけあってルーフレールが標準整備されています。 荷室のボードは樹脂製なので、汚れてもサッとふき取れます。 老舗アウトドアブランドである「OGAWA」とコラボした、かっこいいカータープが公式でオプションとして販売されています。 スズキ ハスラー ハスラーはアウトドア性能だけでなく見た目にもこだわりたいという方にオススメです。 後部座席のみ倒したり座席を全部倒したりと、シートアレンジも自由自在。テントやサーフボードなどのかさばる荷物も余裕をもって積めます。 ハスラーの最低地上高は180mmと高めなので、ちょっとした障害物や轍を乗り越えて走れます。 荷室には、泥や砂で汚れても外して丸ごと洗えるラゲッジアンダーボックスが付属しているので、何かと汚れがちなアウトドアギアもストレスなく収納できます。 オプションのラゲッジネットを取り付ければ天井に収納をプラスできます。 カラーラインナップも豊富で、まん丸のヘッドライトが可愛らしい雰囲気を醸し出しています。 ダイハツ ハイゼットカーゴ この車は商用の軽バンですが、アウトドアに適した性能を持っています。 とにかくたくさん荷物を積みたい方にオススメです。バックドアは特に開口部が大きく、床面地上高が低いため、荷物の積み下ろしが楽々です。 荷室の床面・側面ともに突起がないフラットなデザインになっているため、荷物に傷がつくことがありません。 小回りがいいためカーブの多い山道もストレスなく走れます。 ユースフルナットがたくさん付いているので、特別な加工なしでフックやネットなど様々なものを手軽に取り付けられます。 まとめ アウトドア向きの軽自動車を紹介しました。 適した車種を選べば、海や山などいろんな所に行って気軽にアクティビティを楽しむことができます。 購入をご検討の際は、ぜひ一度お店に足をお運びください! -
 スタッフブログ
2022.10.30
スタッフブログ
2022.10.30
ターボとは一体なに?軽自動車に搭載されるメリットを紹介
軽自動車を選ぶとき「ターボ付き」という記載を見たことがありませんか? ターボと聞くとなんだか速そうだとイメージできると思いますが、具体的に仕組みやメリットは知らない方も多いかもしれません。 そこで今回は、ターボの仕組みとメリット・デメリット、必要なメンテナンスを紹介します。 ターボ付きの軽自動車とは? ターボについて、まずは仕組みとなぜパワフルなのか解説します。 ターボとは空気を送り込む機械 ターボは排気ガスを排出する力でタービンを回し、エンジンに多くの空気を送り込む機械のことです。 エンジンはガソリンを燃やしてパワーを生み出しています。一度に燃やすガソリンの量を増やせばそれだけパワーが出ますが、燃やすには酸素が必要です。 酸素をよりたくさんエンジンに送り込むために、排気ガスを使ってタービンを動かす機械であるターボを使っているということです。 軽自動車はターボと相性が良い! 軽自動車は排気量が660cc以下と決められています。 限られたエンジンの大きさでパワーを出す、つまり多くのガソリンと空気を燃やそうと思うと、補助的にターボを使うのが適しているのです。 軽ターボ車のメリット・デメリット 軽ターボ車のメリット・デメリットを紹介します。 軽ターボ車のメリット ターボ車のメリットは何と言っても「パワーがある」ところです。 ノンターボの軽自動車を運転したことがある方は、上限人数である4人乗っていたり荷物を多く載せていたら上り坂での加速が悪いと感じたことがありませんか? ターボを搭載してパワーがある軽自動車は上り坂でもグイグイ登っていきます。 また、平坦な道でも加速がいいので、高速道路でも周囲の流れに乗りやすくなります。 軽ターボ車のデメリット ノンターボ車と比べて、ターボ車のデメリットは以下の3つです。 ・燃費が悪くなる・値段が高い・エンジンオイルの交換頻度があがる スズキ・ハスラーの上位グレードであるXとXターボを例にして比較してみます。 燃費のカタログ値でXは25.0km/L、Xターボ車は22.6km/Lと、ターボ車の方が2.4km/L燃費が悪いです。 Xの車両本体価格は1,538,900円〜、Xターボは1,639,000円〜と、ターボ車の方がおよそ10万円高価に設定されています。 また、オイルの交換時期はノンターボであるXは走行距離1万kmあるいは6ヶ月ごと、Xターボは走行距離5,000kmあるいは6ヶ月ごととされています。 小さなエンジンがターボにより高負荷がかかっているため、オイル交換の頻度が増えるというイメージです。 軽ターボ車を買うときは新車または新古車がおすすめ! ターボの軽自動車を購入するときは、新車または新古車をおすすめします。 ターボの装置そのものはエンジンの近くにあり、その温度は何百度と非常に厳しい条件で動いています。 ターボは10万kmは壊れませんが、それはエンジンオイル交換を適切にしている場合です。 手入れをされていないターボ車はもっと寿命が短いため、新車または新古車の方が安心でしょう。 ターボ車は大人数で乗れる軽自動車が欲しい方におすすめ! ターボがどのようなものなのか、メリット・デメリットについて解説しました。 ターボを装備するとコスパが悪くなりますがパワーがあるため、4人+荷物が乗った軽自動車でも坂道をグイグイ加速できます。 4人で乗ったり高速道路を走ることが多い方には、軽自動車ターボをおすすめします!